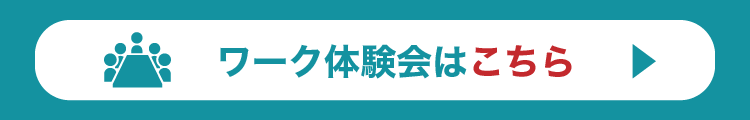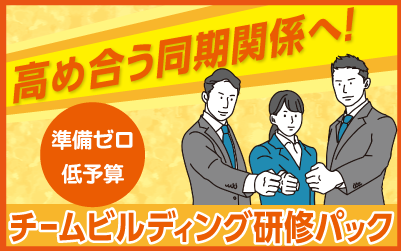研修担当者に聞く、求められる人事のスタンスと研修ストーリー設計とは

たばこ事業本部 事業企画室 採用研修チーム 鈴木 友輔様
最も世界戦略に積極的で、チャレンジングな会社の1社である日本たばこ産業株式会社。
同社は独自の価値観や社風を持ち、人材育成にも力を入れていることで
知られていますが、その中心となる研修担当者様はどのようなスタンスで
若手社員と接し、どのように研修を設計しているのかお伺いしました。
若手社員育成の参考材料としてお役立てください。
1. 内定者が持っているエッジを、入社後も消さず持ち続けさせる。
2. 研修受講者を「群」ではなく「個」として捉え、彼らが自身に向き合う場をいかにつくるか。
3. 研修担当者自身が、人間力を高め、ポリシーを継続することが必要。
INDEX
- Q.まずは貴社の採用方針からお聞かせいただけますか。
- Q .「どうしたい」と聞かれるとありましたが、意思を伝えると、それが通るものなのですか。
- Q.最近の新入社員や内定者も、そういうチャレンジ意欲を持っていますか?
- Q.そうすると、新人研修などで意識を変えることが必要ですよね。研修を行うにあたって、心掛けていることはありますか?
- Q.打ち合わせをしていると、人事の皆さまの研修に対するこだわりや想いの強さを感じます。研修に関わる方々はそういう想いが強い方が多いのですか?
- Q.おっしゃる通り、採用の段階では一人ひとりを見ているはずなのに、研修になると「群」として捉えることは往々にありますね。本来は一人ひとり違いますし、成長課題も違うので、個々人を見ていくべきなんですよね。
- Q.一般的に、3年目は論理的な思考力研修などとテーマが決まってしまっているのですが、貴社の研修は広いテーマで行っていますよね。それはどういうものですか?
- Q.貴社の特徴ですね。一貫性がありますね。鈴木さんご自身に関してですが、今後の研修担当、人事に関わることとして目標はありますか?
Q.まずは貴社の採用方針からお聞かせいただけますか。
(鈴木)
弊社の採用コンセプトは「挑め、ひとのために。自分らしく、JTらしく。」です。弊社には会社のDNAとして昔からすごく個性的な人たちが集まっているので、まさにそういう「自分らしさ」という強い個性を持っている人たちに集まってもらいたいと思っています。
もうひとつ、弊社の特徴としてあるのは、自分の意思をしっかり持って、自分はこうしたいと考えて、そこをベースに仕事をするということです。私も新入社員のときから、指示をされるだけでなく、「鈴木はどうしたいの」と聞かれてきました。自分も新入社員に対してそうしているのに何年か経って気づきましたね。そういうカルチャーを通して、一人のプロフェッショナルを作り出す。そしてそのプロフェッショナルとプロフェッショナルがチームとして構築されたときに、より高いシナジーが生まれていくのだと思っています。そのようになれる人たちと一緒に仕事をしていきたいと思っているので、そんな「自分らしさ」を持っているということに焦点を置いて採用しています。
Q .「どうしたい」と聞かれるとありましたが、意思を伝えると、それが通るものなのですか。
(鈴木)
「どうしたい」という言葉は、to doだけでなくto beも包含されていると捉えています。そして、shouldという文脈ではあまり語りません。wantで話すように思います。そのwantが自分の気持ちだけでやりたいのであれば単なるエゴですが、そこに課題があって、それをすることに意義があり、そこに飛び込みたい、チャレンジしたいと思えば少なくとも否定されることはないです。個人的な経験では、goと言われることが多かったように思います。
Q.最近の新入社員や内定者も、そういうチャレンジ意欲を持っていますか?
(鈴木)
採用の段階では持っているように思います。でも、いざ会社の中に入ってしまうと、自分の中でこれを「すべき」であるとか、この型にはまらなければ「ならない」、などと無意識でそう思ってしまうきらいがあるんです。採用の段階では彼らなりのエッジとか、光るものがあったはずなのですが、その出し方がわからなくなってしまう。自分で蓋をしてしまうんですね。そういうところは大きな課題だと思っています。
Q.そうすると、新人研修などで意識を変えることが必要ですよね。研修を行うにあたって、心掛けていることはありますか?
(鈴木)
大事にしていることは「研修じゃなければできないことはなにか」を突き詰めて考えることです。私の担当している研修は集合型研修なので、受講者は研修の場にお互いに刺激し合えるいい仲間がいます。そこでお互いにいい気づきと学びを渡し合える、そんな土壌をしっかり作るということを大事にしています。会社から課題を出すよりも、彼ら自身で研修に対する意味を見つけたり、自分に足りないものは何か考える。そういう風に自分自身でストーリーを紡ぎ出していける研修が大事だと思っています。

Q.打ち合わせをしていると、人事の皆さまの研修に対するこだわりや想いの強さを感じます。研修に関わる方々はそういう想いが強い方が多いのですか?
(鈴木)
そうですね、私の意見ですが、採用のときには一人ひとりの個性と向き合ってきたはずが、研修というステージになった途端、一人ひとりをきちんと見ないのはおかしいと思うんです。採用のときにそれだけ熱量をもって採用したにも関わらず、成長支援というステージのときに単純にコンテンツだけを実行するのは違うのではないかと。そうではなく、一人ひとりにどうやって向き合うか。そう考えたときに、ミスリードをしたくなかったり、こちら側の熱や思いをどうしても伝えたかったり。どうしてもこだわりを持たざるを得ないと思いますね。
Q.おっしゃる通り、採用の段階では一人ひとりを見ているはずなのに、研修になると「群」として捉えることは往々にありますね。本来は一人ひとり違いますし、成長課題も違うので、個々人を見ていくべきなんですよね。
(鈴木)
そうですね。そういう考えは周りの人事にも伝えるようにしています。画一的に、何年目だからロジカルシンキングの研修を、という会社側のシナリオに沿った研修も実はずれているのではないかと思っていて、彼らがこれをしたい、学びたい、成長したいという、それぞれ違うポイントを持つ中で、どういう場を適時適切に提供できるかが大事だと思っています。それが、本人が紡ぐ自分のストーリーなんですよね。

Q.一般的に、3年目は論理的な思考力研修などとテーマが決まってしまっているのですが、貴社の研修は広いテーマで行っていますよね。それはどういうものですか?
(鈴木)
例えばですが2年目にやっているのが、自分の仕事としっかり向き合うというテーマで行う研修です。我々はメーカーで、わかりやすいバリューチェーンがあるので、その文脈の中で研修を作るのですが、それを1年目から体感させていきながら、2年目には振り返りを行います。
会社として大きな仕事の流れがあるなかで、自分自身がやるべき役割は何なのか、ということに向き合わせる、そういう研修になっています。何に向き合うかも本人次第です。ですが、きちんと振り返って考える。そういう時間は誰にでも必要だと思っているので、そういうことをやっています。
Q.貴社の特徴ですね。一貫性がありますね。鈴木さんご自身に関してですが、今後の研修担当、人事に関わることとして目標はありますか?
(鈴木)
まずは、自分自身が人間力を高めるということを意識したいと思っています。研修をつくったり、考えたり、偉そうに抗弁を垂れるときに、自分自身はどうなんだという問いかけを必ずするようにしています。自分がそこまで人間力が高くないにも関わらず、偉そうなことをするのは肌に合わないんです。彼らに何かを求める以上、自分自身をそこより先に高めていきたいというのがやりたいことのひとつです。
二つ目が、ポリシーの継続です。私自身1年目からずっと言われ続けているのが「人事という言葉は「ヒトゴト」とも読める。人事たるもの「ヒトゴト」の仕事は絶対にするな」という教えです。じゃあどういう仕事をしたいかとなったときに、人事として「ヒトリヒトリノコト」を考え、そこに向き合う、そういう仕事をしっかりやりたいと。そう思い続けてやってきているので、これからもそこはブレずにやっていきたいと思っています。